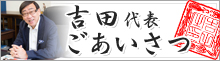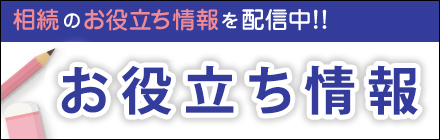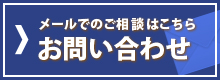相続税額の計算上、相続財産から差し引くことができる葬式費用 2021.7.26
葬式費用は、本来、遺族が負担すべき費用であり、亡くなった人の債務ではありません。 しかし、人が亡くなったことにより必然的に生ずる費用であり、相続税の計算上、債務と同様に相続財産からが差し引くことができます。 そこで、葬儀費用として差し引きできるもの、できないものを簡単にご説明します。 まず、葬式費用となるものとして、 ①葬式や葬送に際し火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用 ②ご遺体やご遺骨の回送にかかった用 ③お通夜の席での食事代など、葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用 ④葬式…
固定資産税納税通知書が届かない理由 2021.7.12
土地や家屋を持っておられる方には、毎年春頃(各市町村によって違います)に各市町村から固定資産税の納税通知書が送られてきます。 しかし、固定資産を所有しているのに納税通知書が届かないケースがあります。 理由は4点考えられます。 1.引越し等により、送付先が変更されている 納税通知書の送付先は市内の転居、市外への転出の場合を除き、住民票の異動を行っても自動的に送付先は変わりません。 そのため前述以外の異動がある場合は、古い住所へ納税通知書が送付され、宛て所不明で返戻されている可能性があります。 その…
死後事務委任契約について 2021.7.5
人が死亡すると、葬儀の主宰、役所への行政手続き、病院代等の清算、年金手続き、クレジットカードの解約など、様々な事務手続きが発生します。 一般的に、これら事務手続きは家族や親族が行いますが、身寄りがいない方の場合には誰もその作業をしてくれる人はいません。 高齢化社会が進み、子供がいない夫婦が増え、家族関係が薄くなった現代においては、この死後事務を行う方が誰もいないまま亡くなる方が後を絶ちません。 このように、死後の煩雑な事務手続きを生前にうちに誰かへ委任しておくことができる制度が「死後事務委任契約…
従業員の在宅勤務手当の課税について 2021.6.28
国税庁は在宅勤務に関する企業からの問い合わせに対応するため、2021年1月に「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公開しました。 その中で、在宅勤務(テレワーク)に関する通信費、電気料金、在宅勤務手当などについて「通常必要な費用を精算する方法」による支給は非課税とする指針を発表しています。 今回は具体的な例と計算方法を一部ご紹介します。 ■通信費■ 業務目的の通話料(基本使用料を除く)については、通話明細等により業務のための通話料金を確認します。 ただし、業務のための通話…
税務署の機構改革 ~続~ 2021.6.21
以前このページでも少し書きましたが、国税庁は令和元年7月より申告書等の入力など、事務処理の効率化を図る目的で、申告書処理センターの設置を始めています。 大阪国税局管内においては令和3年6月現在、東淀川・北・神戸の3センターが稼働しています。 これに加え、兵庫県関連では令和3年7月12日から、神戸センターに兵庫税務署が加わることとなります。 7月12日以降、兵庫税務署管轄の納税者が申告書等を郵送する場合、神戸・灘・須磨・長田署と同じく、税務署事務処理センター(神戸センター)に送付することになります…
株式会社と合同会社 2021.6.14
会社の設立=株式会社と考えられる方は多いと思いますが、会社形態として合同会社というものがあります。 合同会社は2006年5月1日に施行された会社法で新たに設けられた会社形態であり、2020年に設立された法人が118,999社あるうち、合同会社が33,236社と約4分の1を占めていて、年々設立割合・設立数は増加しています。 株式会社と合同会社の違いとして、株式会社は経営者(社員)と出資者(株主)が分離しているのに対し、合同会社は経営者と出資者が一体化しています。 経営方針について見ると、株式会社は…
土地贈与契約書に貼り付ける印紙 2021.6.7
印紙が必要となるケースとして、一定以上の金額を受領した際に領収書を作成した場合や契約書を作成した場合などがあります。 売買契約書等を作成した際には、その契約書の記載金額に応じた印紙を貼らなければなりません。 では土地を贈与しその贈与契約書に土地の評価額を記載した場合には、いくらの印紙を貼らなければならないのでしょうか? 不動産を他人に移転させることを内容とする契約書については、対価を受けるかどうかを問わず、印紙税法別表第一 (第1号の1文書)(不動産の譲渡に関する契約書)に該当します。 つまりこ…
相続における減価償却費 2021.5.31
通常の事業の場合、中古品を買うと減価償却の耐用年数が短くなりますが、相続により取得した減価償却資産の耐用年数は、中古資産に係る見積もりでの使用可能期間に基づいた年数とすることはできません。 相続で取得した資産が減価償却資産である場合の取得価額は、その資産を相続により取得した方が引き続き所有していたものとみなした場合において、減価償却資産の取得価額に相当する金額とします。 そのため相続で取得した事業用の不動産や車両・備品等は亡くなった方から取得価額、耐用年数、経過年数、未償却残高を引き継ぐこととな…
無効な遺言書 2021.5.24
自筆の遺言書は、故人が最後の想いを書面に遺すものですが、書き方を間違えるとせっかくの意思が反映されません。 無効になるパターンとして、以下のようなものが多いのでご注意ください。 ①自筆で書かれていないもの 遺言者本人が自筆で作成していないと、自筆証書遺言書は無効になります。 ただし、民法改正により、遺言書に添付する財産目録に限ってはパソコンや代筆による作成が認められるようになりました。 なお、音声や動画等のデータによる遺言は認められません。 ②日付がない、日付があいまいな遺言書 作成日が記載され…
相続放棄(限定承認)について 2021.5.17
相続放棄と間違いやすいものに、「限定承認」という相続手続きがあります。 まず、その限定承認を理解するために、単純承認と限定承認の違いから理解する必要があります。 単純承認 ○財産も借金なども全て無条件に承認する相続です。 限定承認 相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続することです。 すなわち、相続する際に借金などが、相続する財産よりも多い(債務超過)と見込まれるときには、被相続人から承継するプラスの相続財産の限度で、亡くなったひとの借金などの支払をするという、限度付きの相続…
![神戸・芦屋・西宮でお探しなら!行政書士 オアシス相続センター[吉田博一 税理士事務所]](/wordpress/wp-content/themes/greenpoint-milanda/images/common/header/header_logo.png)