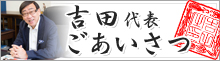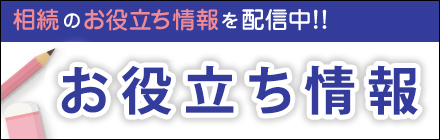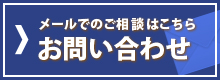税金を払いすぎた場合はどうなる?? 2021.5.6
税金を納めてから申告内容の誤りに気がついた!というような場合、納め過ぎた税金を還付してもらうよう請求することができます。これを「更正(こうせい)の請求」といいます。 ■更正の請求とは 過去の申告について、税金を適正な額より納め過ぎていた場合に、納め過ぎていた部分の税金の返金を求める手続きです。 所得税や贈与税、法人税についても更正の請求手続が存在しますが、請求ができるのは国税通則法によると申告期限から5年とされています。(国税通則法23条) ただし、裁判所の判決など後発的な事由により再計算が必要…
税務署の機構改革? 2021.4.27
新年度が始まり、どこの職場でも人の入れ替わりがある季節になりました。 個人・法人の確定申告や相続税の窓口である税務署も同じで、4月から新規採用の職員が配置されたようです。 例年であれば、新規採用の新人はまず管理運営部門に配属されます。 そこで税金の収納、納税証明の発行、税務相談などを担当して諸税目の知識を蓄え、1年後に個人課税部門や法人課税部門へと配置換えされていきます。 4月に納税証明の取得や税務相談のために税務署を訪れると、初々しい若者が先輩の隣に立っている姿が見受けられたものです。 5月頃…
特別利子補給助成金の収益計上時期について 2021.4.19
日本政策金融公庫(日本公庫)、沖縄振興開発金融公庫(沖縄公庫)、商工組合中央金庫(商工中金)及び日本政策投資銀行から「新型コロナウイルス感染症特別貸付」や「危機対応業務(危機対応融資)」といった借入金の融資を受けた方は多いかと思われます。 特別利子補給助成金とは、これらの借入金について、一定の要件を満たしている方(事業規模ごと(日本標準産業分類によって分類される業種ごとに、常時使用する従業員数に応じての判定)に定められた売上高の要件(売上高が一定割合以上減少していること。 詳しくは新型コロナウイ…
振替依頼書のオンライン提出 2021.4.12
個人が行う所得税や消費税の確定申告に係る納税については、金融機関に出向いて行う納付書による納税の他に、納付金額によってはコンビニ納付やクレジットカードによる納付、これら以外に振替納税などの方法があります。 毎年確定申告をされている方の多くは、その支払方法の中でも振替納税を利用されている方が多いかと思います。 振替納税については、振替納税を利用したい最初の納付に係る確定申告書の申告期限までに振替依頼書に必要事項と銀行の届出印を押印した上で税務署に提出しなければいけません。 金融機関の振替手続になる…
相続税法における障害者控除 2021.4.5
相続税の障害者控除とは、相続人の内に障害がある方がおられる場合に相続税が減額される制度です。 相続税の税負担が、障害者の生活資金にまで影響を及ばないようにすることを目的としています。 この障害者控除を適用するためには、 ⑴日本国内に住所を有すること日本国内に住所がなくても、 ①日本国籍を有している ②被相続人または相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所がある となっている場合は適用されます。 ⑵障害者であること ①一般障害者 ・身体障害者手帳上における障害等級が3級~6級 ・精神障害者保健…
介護保険サービスで医療費控除になるもの、ならないもの 2021.3.30
近年 高齢者サービスには様々な施設や形があります。 これらで受けるサービスが医療費控除の対象となるかどうかみてみましょう。 介護保険で受けられるサービスには福祉サービスと医療サービスの2種類があります。 医療系サービスの場合は、治療を目的としたサービスであるため医療費控除の対象となりますが、福祉系サービスは治療を目的としていないため医療費控除の対象となりません。 ただし、福祉系サービスでも医療控除の対象となるケースがあります。 それは医療系サービスを併用している場合です。 主な医療系サービスには…
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除 2021.3.23
株式等の売買を行い譲渡損失が出た場合、確定申告時に注意が必要となりますので以下を参考にして下さい。 その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この特例の適用を受けて既に前年以前に控除されたものを除く。)を有する場合には、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額は生じなかったものとみなす」という 措法第37条の11 第1項後段の規定にかかわらず、その上場株式等に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、その確定申告書に係る年分の上場株式等に係る譲渡所得等…
2021年4月1日から実施!消費税「総額表示」のご準備はできてますか? 2021.3.15
消費税が8%から10%(軽減税率8%含む)へ引き上げになり約1年半が経過しました。 総額表示とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う事業者が、値札やチラシなどでその取引価格を表示する際に、消費税額を含めた価格を表示することをいいます。 実はこの総額表示は2004年から義務付けられているのです。 しかし、消費税が5%から8%、さらに10%と段階的に引き上がることが決まり、総額表示のままでは増税のたびに値札や印刷物などを訂正する作業とコストが発生することが想定されたため、特別措置法(消費税転嫁…
配当所得 2021.3.8
上場株式等の配当金の申告については、以下の3通りの方法があります。 1.確定申告をしない。 2.総合課税として所得税の確定申告をする。 3.所得税は総合課税で確定申告をして、住民税は申告不要制度を利用する。 1の場合には分離課税となり、税率は国税15.315%、地方税5%の源泉税が天引きされます。証券会社等の特定口座を利用している方で、上場株式等の譲渡損がある場合には損益通算することもできます。 2の場合には配当所得を給与所得や年金所得と合算して、配当控除を受けることもできます。還付金にも期待で…
扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除の判定基準の見直し 2021.3.1
2020年から扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除の対象となる判定上の合計所得金額が10万円引き上げられました。 しかし、必ずしも扶養控除の対象となる親族の範囲が広がったわけではありません。 扶養親族の所得が給与所得や公的年金であれば、2020年以降は給与所得控除額や公的年金等控除額が10万円引き下げられているためです。 そのため、扶養親族の所得が給与または公的年金のみである場合において、収入金額ベースの判定基準は変わっていないと言えます。 しかし、合計所得金額が10万円引き上げられたことで影響…
![神戸・芦屋・西宮でお探しなら!行政書士 オアシス相続センター[吉田博一 税理士事務所]](/wordpress/wp-content/themes/greenpoint-milanda/images/common/header/header_logo.png)